はじめに
こんにちは!そらいろドクターです。(はじめましての方、著者プロフィールはこちら)
今回取り上げるのは、「肺塞栓症(はいそくせんしょう, Pulmonary Embolism, PE)」。
PEは心筋梗塞、脳卒中に次いで3番目に多い心血管系の救急疾患とも言われており、診断の遅れは命取りになりかねません。
しかし、このPE、診断が一筋縄ではいかない厄介者。症状は非特異的で、多彩な臨床像を呈します。
実際、PEと診断された方の3割には明らかなリスク因子がなく、4割は酸素飽和度が正常だったというデータもあるようです。血液検査や心電図、胸部X線だけでは確定診断はできません。
今回は、複数の文献、Up to Dateの知見に基づいたPEのリスク層別化と診断アプローチについて、私自身の思考プロセス(【私見】)を交えて記事にしました。
この記事を読むことで
- UpToDateや最新レビューに基づいたPE診断アルゴリズムの流れを理解できる。
- PE診断における「事前確率評価」の重要性と各ツールの使い方・注意点がわかる。
- Dダイマー(年齢調整、YEARSアルゴリズム)の適切な解釈と限界を理解できる。
- 診断後のリスク評価と治療方針決定への繋がりを理解できる。
(想定読了時間:約25分)
診断の基本戦略:血行動態の安定性でまず分類
PEが疑われる患者さんのアプローチは、まず血行動態が安定しているか否かで大きく分かれます。UpToDateのアルゴリズムもこの分類から始まります。
- 血行動態不安定な患者(高リスクPE疑い):
低血圧、ショック、心停止などで生命の危機が差し迫っている患者を指します。
この場合は、臨床経過やベッドサイド心エコーや下肢静脈エコーから迅速に判断し、診断と治療(蘇生、早期の抗凝固療法、血栓溶解療法など)を同時に進める必要があります。
※詳細は専門的なトピックとなるため、本記事では主に血行動態が安定している患者さんの診断戦略に焦点を当てます。 - 血行動態安定な患者:
ここからが本記事のメインテーマです。主に外来/救急外来で比較的落ち着いている患者に対する体系的な診断アプローチを以下に記載していきます。
ステップ1:事前確率の評価 (PTP)
血行動態が安定している患者さんでPEを疑った場合、最初に行うべきは検査前確率(Pre-test Probability:PTP)の評価です。これにより、その後の検査戦略が大きく変わってきます。
臨床的ゲシュタルト vs 臨床予測ルール
PTPの評価には、経験豊富な医師の「臨床的ゲシュタルト」も参考にされます。
(Penaloza A et al. Ann Emerg Med. 2013;62(2):117-124.e2)
しかし、客観性と標準化のため、臨床予測ルールが広く用いられています。代表的なものにWellsスコアや改訂ジュネーブスコアがあり、有名なので皆様もご存知のことと思います。
Wellsスコア(PE用)
- □ 深部静脈血栓症 (DVT) を示唆する症状や徴候 +3点
- □ PE以外の診断の可能性が低い +3点
- □ 心拍数 > 100回/分 +1.5点
- □ 過去4週間以内の手術または3日以上動かないことがあった +1.5点
- □ DVTまたはPEの既往 +1.5点
- □ 喀血 +1点
- □ 活動性の悪性腫瘍(過去6ヶ月以内の治療、または緩和ケア中)+1点
リスク分類(3段階): 低リスク (< 2点)、中等度リスク (2~6点)、高リスク (> 6点)
※修正Wellsスコア (2段階分類)は、PEの可能性が高い (likely, スコア > 4点) か低い (unlikely, スコア ≤ 4点) かに分類する方法
【私見】
修正Wellsスコアも2段階分類で使いやすいのですが、やはり古典的なWellsスコアの方が過去の様々な検証・臨床経験に裏打ちされていることや3段階のリスク層別化により特に中等度リスク群を含めて不要な画像検査を効果的に削減できる点で有用と考えてます。
もちろんWellsスコアも完璧では無く、特に「PE以外の診断の可能性が低い」という項目は評価者の主観が入りやすいため注意が必要です。状況によっては改訂ジュネーブスコアも参考により客観的な複数の視点からPTPを考えるようにするようにしています。結局どのスコアを用いるにしても、その限界を理解し、個々の患者背景と臨床像を総合的に判断することが最も重要です。
ステップ2:PTPに応じた診断戦略
PTPを評価したら、そのリスクの程度に応じて具体的な検査戦略を選択します。
A. 低PTP群 (Low probability of pulmonary embolism)
PTPが低いと判断された患者さん(例: Wellsスコア < 2点)に対しては、まず「PERCルール (Pulmonary Embolism Rule-out Criteria)」の適応を検討します。
以下の8項目すべてを満たせば(PERC陰性)、PEの可能性は1%未満とされ、追加検査なしで安全にPEを除外できます。
(Kline JA et al. J Thromb Haemost. 2008;6(5):772-780)
これにより不要なDダイマー検査や画像検査を回避できます。
(Freund Y et al. JAMA. 2018;319(6):559-566)
PERCルール(8項目すべて陰性でPEを除外)
- 年齢 < 50歳
- 心拍数 < 100回/分
- 室内気での SpO\(_{2}\) ≥ 95%
- 喀血なし
- エストロゲン製剤の使用なし
- 最近4週間以内の手術や外傷歴なし (入院を要するもの)
- DVTやPEの既往なし
- 片側の下肢腫脹なし
PERCルールが1項目でも陽性の場合、またはPERCルールが適用できない場合(例:入院患者、PTPが低確率とは言えない場合など。PERCはPEの有病率が低い集団で検証されています)は、次に高感度Dダイマー検査へ進みます。
- Dダイマー < 500 ng/mL (or後述の調整カットオフ値未満):
➡ PEは除外されたとみなされ(<2%)、追加検査は不要 - Dダイマー ≥ 500 ng/mL (or後述の調整カットオフ値未満):
➡ 画像検査(通常は造影CT)が必要
B. 中等度PTP群 (Intermediate probability of pulmonary embolism)
PTPが中等度(例: Wellsスコア 2~6点)と判断された患者さんには、高感度Dダイマー検査を行います。
- Dダイマー < 500 ng/mL(or後述の調整カットオフ値未満):
➡ PEは除外されたとみなされ(<2%)、追加検査は不要 - Dダイマー ≥ 500 ng/mL (or後述の調整カットオフ値未満):
➡ 画像検査(通常は造影CT)が必要
※心肺予備能が低い患者や、中等度PTPの中でも高めの範囲(例: Wellsスコア 4~6点)の患者では、Dダイマー検査なしで直接画像検査を行うことも考慮されます。
(UpToDate: Intermediate probability of pulmonary embolismより)
C. 高PTP群 (High probability of pulmonary embolism)
PTPが高い(例: Wellsスコア > 6点)と判断された患者さんでは、Dダイマー検査はPEを除外するには不十分であり、Dダイマー陰性でもPEの可能性が5%以上残ることもあるとされるため、、原則としてDダイマーを参考にせず(あるいは測定せず)、直ちに造影CT(または代替の画像検査)を行います。
Dダイマーのカットオフ ー 年齢調整とYEARSアルゴリズム
Dダイマー検査の特異度を上げるために、以下の調整カットオフ値が有用です。
- 年齢調整Dダイマー:
D-dimer値は加齢とともに上昇する傾向があり、50歳を超える高齢の患者さんに対して従来の固定カットオフ値(例: <500 ng/mL)を用いると、実際には肺塞栓症(PE)がないにもかかわらずD-dimerが陽性(偽陽性)となりやすく、結果としてD-dimer検査の特異度が低下することが懸念されます。
50歳以上の患者さんでは、カットオフ値を「年齢 × 10 ng/mL (FEU単位の場合)」とすることでこの問題を解決できるのでは無いかと考えられています。
(Righini M et al. JAMA. 2014;311(11):1117-1124)
- YEARSアルゴリズム:
臨床的確率(Wellsスコアの3項目:①DVT徴候、②喀血、③PEが最も可能性の高い診断)とDダイマー値を組み合わせる診断戦略です。「日本集中治療医学会専門医テキスト 第4版」にもこのアルゴリズムが紹介されています。
(van der Hulle T et al. Lancet. 2017;390(10091):289-297; UpToDate: YEARS criteria)
《YEARSアルゴリズム》- 上記3つのYEARSクライテリアが0項目 and Dダイマー < 1000 ng/mL → PE否定
- 上記3つのYEARSクライテリアが1項目 and Dダイマー < 500 ng/mL → PE否定
- 上記以外 → CTPA考慮
※YEARSクライテリア0項目 and Dダイマーが年齢調整カットオフ値未満の場合、or YEARSクライテリア1項目以上でDダイマーが500 ng/mL未満の場合にPEを除外するという、より詳細なプロトコルも紹介されています。
(Freund Y et al. JAMA. 2021;326(21):2141-2148)
【私見】
高齢化の進む日本において、年齢調整Dダイマーをカットオフとする方法は非常に有用です。またYEARSアルゴリズムは、特に救急外来のような忙しい環境で、安全性を保ちつつ造影CTの施行を減らす際に非常に有用なツールだと感じています。
特定のカットオフに依存せず、症例毎に複数のカットオフで診断フローの一致・不一致を検証して、感度・特異度を意識して適切なカットオフを用いる姿勢が重要と考えます。
ステップ3:画像診断と補助検査の役割
上記のアルゴリズムで画像検査が必要と判断された場合、以下の検査を検討します。
造影CT(CT肺動脈造影;CTPA)
現在のPE診断における第一選択の画像診断法です。
(Stein PD et al. N Engl J Med. 2006;354(22):2317-2327)
感度・特異度が高く、PEの確定だけでなく、右室負荷の評価や他の胸部疾患の鑑別も可能です。
その他の画像検査とバイオマーカー
- 換気血流シンチグラフィ (V/Q scan):
CTPAが施行できない患者さんや被曝を避けたい場合に有用です。結果はPTPと組み合わせて解釈します。 - 下肢静脈エコー (CUS):
PEの除外はできませんが、DVTが確認されれば治療開始の根拠となりえます。 - 心エコー (POCUS含む):
右心負荷所見(右室拡大、McConnell徴候、D-shape、TAPSE低下などは重症度判定や予後予測に重要です。特に血行動態不安定例では必須の評価です。 - 心筋マーカー(トロポニン)、心不全マーカー(BNP / NT-proBNP)、血清乳酸値:
これらは主にPE診断後のリスク層別化や予後予測に用いられます。
【私見】
救急外来でのPOCUSの活用は、診断の迅速化に大きく貢献します。PEを疑えば、下肢静脈エコーでDVTを探し、心エコーで右心負荷のサインを確認する習慣をつけることが、見逃しを防ぎ、重症度を早期に把握する上で非常に大切だと考えています。
ステップ4:重症度評価と治療方針決定
PEの診断が確定したら、次は重症度評価です。そのための標準的なツールが「PESIスコア (Pulmonary Embolism Severity Index)」または、より簡便な「sPESI (simplified PESI)」です。これらは30日死亡リスクを予測するのに役立ちます。
(Aujesky D et al. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(8):1041-1047 [PESI]; Chagnon I et al. Am J Emerg Med. 2012;30(9):1886-1891 [sPESI])
PESIスコアの評価項目と点数
- 年齢:年齢そのもの(点)
- 男性:+10点
- 癌の既往:+30点
- 心不全の既往:+10点
- 慢性肺疾患の既往:+10点
- 心拍数 ≧ 110回/分:+20点
- 収縮期血圧 < 100 mmHg:+30点
- 呼吸数 ≧ 30回/分:+20点
- 体温 < 36℃:+20点
- 意識変容:+60点
- 室内気 SpO\(_{2}\) < 90%:+20点
リスク分類(30日死亡率の目安):
クラスI (≤65点, 〜1.1%)
クラスII (66-85点, 〜3.5%)
クラスIII (86-105点, 〜7.1%)
クラスIV (106-125点, 〜11.4%)
クラスV (>125点, 〜24.5%)
(Aujesky D et al. Am J Respir Crit Care Med. 2005;172(8):1041-1047など)
sPESI (simplified PESI) スコアの評価項目(各1点)
- 年齢 > 80歳
- 癌の既往
- 慢性心肺疾患の既往
- 心拍数 ≧ 110回/分
- 収縮期血圧 < 100 mmHg
- 室内気 SpO\(_{2}\) < 90%
リスク分類: 低リスク (0点, 30日死亡率〜1%)、高リスク (≧1点, 30日死亡率〜10.9%)。
これらのスコアと心エコーでの右室機能評価やバイオマーカーを総合的に評価し、治療方針を決定します。
近年は、迅速な治療方針決定を支援する多職種チーム「PERT (Pulmonary Embolism Response Team)」の役割も重要視されています。
(Kabrhel C et al. Chest. 2016;150(2):384-393; Rivera-Lebron B et al. Clin Appl Thromb Hemost. 2019;25:1076029619853037)
まとめ
肺塞栓症(PE)の診療は、多様な症状の中から可能性を拾い上げ、適切な検査戦略によって迅速かつ正確に診断し、重症度に応じた治療へと繋げる必要があります。
PE診断のアルゴリズム
- 臨床所見や病歴から事前確率(主にWellsスコア)を評価。
- 事前確率が非常に低い(かつ非入院患者などの適用条件を満たす)と判断されれば、PERCルールで安全に除外できるか検討。PERC陰性ならPE否定的。
- PERC適用外または陽性の患者、あるいは初めからPTPが低~中等度と判断される患者には、YEARSアルゴリズムを適用。
- YEARSクライテリア 0項目 + Dダイマー陰性 → PE否定的
- YEARSクライテリア≥1項目 + Dダイマー陰性 → PE否定的
- 上記以外(Dダイマーが各閾値以上)→ 次のステップへ
- 事前確率が高い(例: Wells > 6)、またはYEARSアルゴリズムにより除外不可となった群には、禁忌がなければ造影CTで確定診断。
- PEと診断がついたら、PESIスコア(またはsPESI)、バイオマーカー、心エコー所見などで重症度評価を行い、治療方針を決定。
※血行動態不安定な高リスクPEでは、ECMO導入後のCTPAも考慮。
このアルゴリズムに沿って思考することで、診断の見逃しや遅れ、過剰な検査を避け、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供することが可能になります。
この記事が、先生方の日常診療の一助となれば幸いです。
参考文献:
– UpToDate: Thompson BT, Kabrhel C, Pena C. Clinical presentation and diagnostic evaluation of the nonpregnant adult with suspected acute pulmonary embolism. (Accessed on 2025/05/08)
– Thomas SE, Weinberg I, Schainfeld RM, Rosenfield K, Parmar GM. Diagnosis of Pulmonary Embolism: A Review of Evidence-Based Approaches. J Clin Med. 2024 Jun 26;13(13):3722. doi: 10.3390/jcm13133722.
– Franchin L, Iannaccone M. Limitations and Future Perspectives on Pulmonary Embolism: So Far, So Good. Interv Cardiol. 2025;20:e11. doi: 10.15420/icr.2024.45.
– Piazza G. Cover Story | Pulmonary Embolism: A Clinical Approach. Cardiology Magazine (ACC). Feb 01, 2025.
– 日本集中治療医学会 編. 日本集中治療医学会専門医テキスト 第4版.
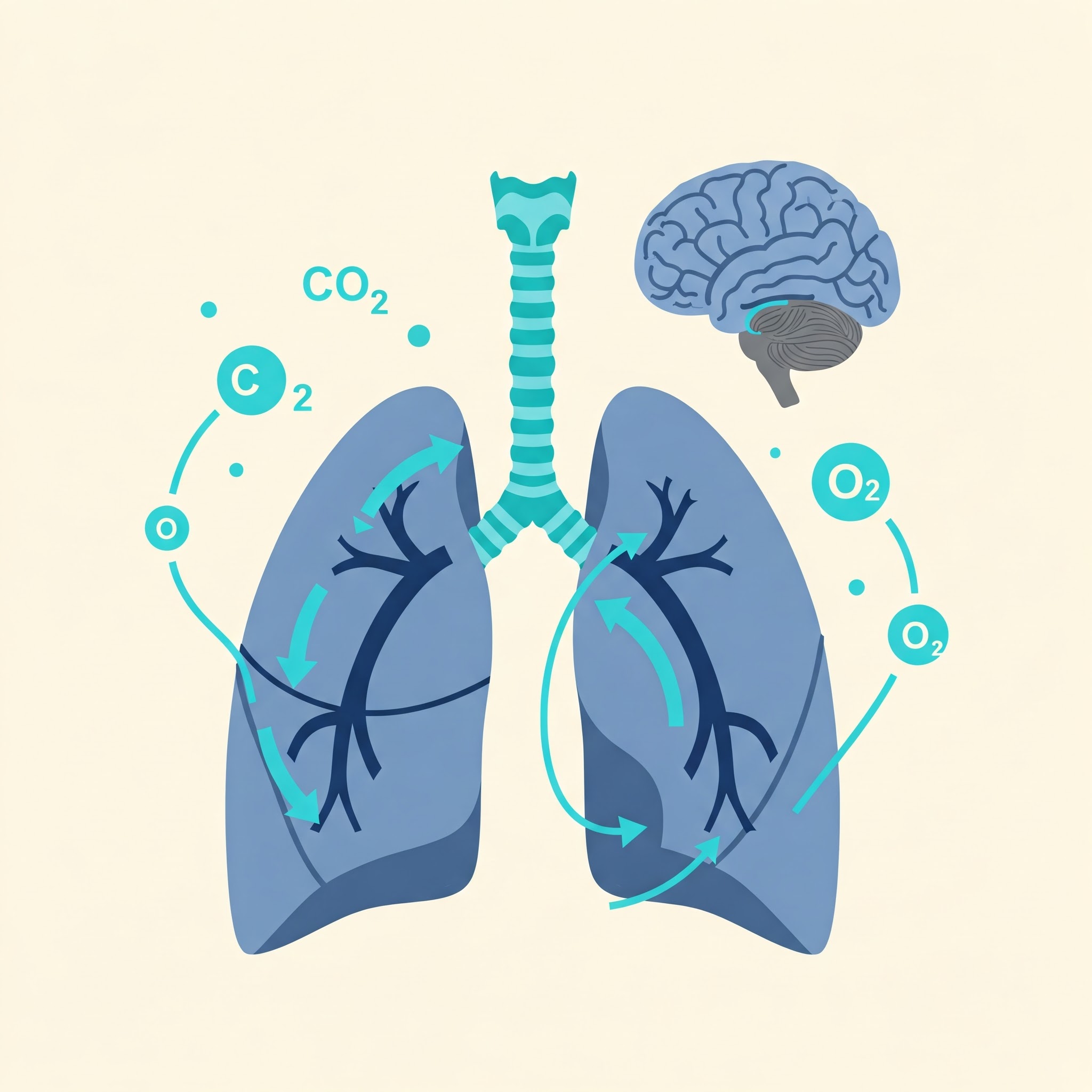


コメント